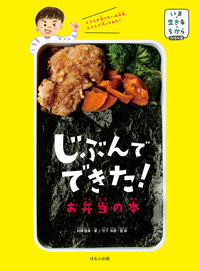社会課題解決の現場で働く方々からお話を伺い、その内容をインタビュー記事として発信するWebメディア「ソーシャルウォーカー(Social Walker)」。市⺠活動やソーシャルビジネスに焦点を当て、事業内容や背景にある社会課題、行政だけでは課題が解決されない理由などを独自インタビューを基に発信しています。
第12回目は、「一般社団法人きほんの木」の代表理事である杉崎 聡美(たかせ さと美)さんにお話を伺いました。
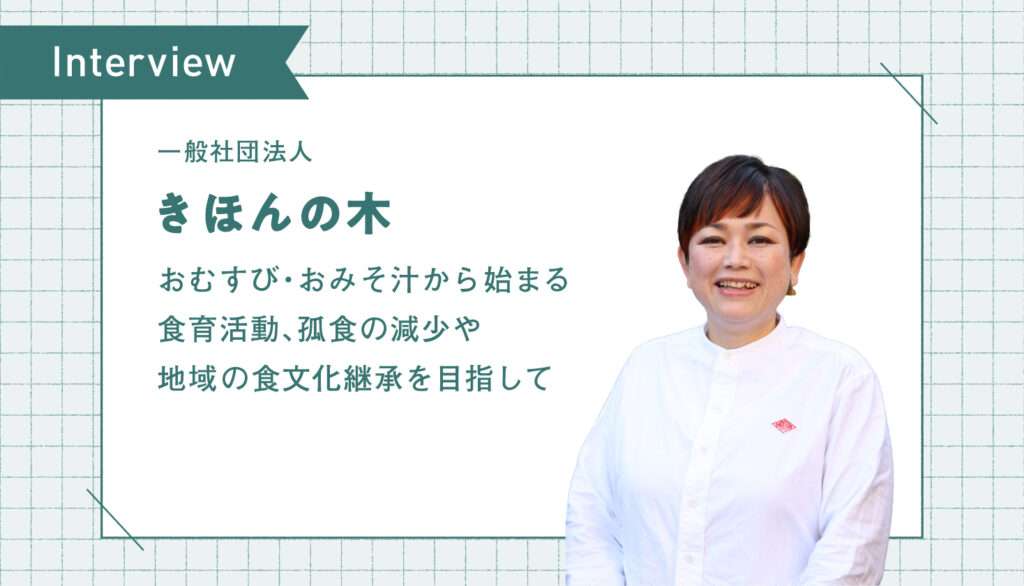
生きていく上で欠かすことのできない“食”。便利な世の中になり、料理をしなくても手軽に食事ができるようになった現代社会ですが、食生活の悪化による生活習慣病の発症や日本食文化が継承されないといった問題も起こっています。
一般社団法人きほんの木では、“おむすび”と“おみそ汁”を基本とした食育活動を通じ、子どもの孤食問題や日本食文化の継承などに取り組んでいます。
団体紹介

| 名称 | 一般社団法人きほんの木 |
| 公式HP | https://ecolle-ocatte.studio.site/kihonnoki (みんなの放課後お料理教室 エコール・オカッテ:https://ecolle-ocatte.studio.site/) |
| 事務所所在地 | 東京都日野市 |
| 問合せ先 | https://ecolle-ocatte.studio.site/kihonnoki |
| 事業内容 | 食育の普及・振興、食文化の醸成にまつわる諸活動 |
今回お話を伺った人

杉崎 聡美(すぎざき さとみ)さん
ビジネスネーム:たかせ さと美
「一般社団法人きほんの木」代表理事
「ナチュラルフレンチ kizagisu」代表
■プロフィール
外資系ホテルなどにて修行したフレンチの料理人。
サイボーズと東大和市主催の地域クラウド交流会にて、ビジネスプランが優勝したことを機に食育活動向けの一般社団法人を立ち上げる。
第5回日経ソーシャルビジネスコンテストファイナリスト『未来を担う子供達へ 日本のソールフード「おむすびとおみそ汁」で食育を』
――たかせさん、本日はどうぞよろしくお願いします。
たかせさん:よろしくお願いします。
“おむすび”と“おみそ汁”作りを基本とした食育活動を全国で展開
――はじめに、「一般社団法人きほんの木」の事業内容を教えていただけますか。
たかせさん:全国で子ども向けの食育活動に取り組んでおり、主に「おむすび講座」と「みんなの放課後食育教室」を不定期で開催しています。その他、STEAM教育を手がける株式会社ヴィリング様との共催で、食育STEAM授業も行っています。
――「おむすび講座」と「みんなの放課後食育教室」は、どのくらいの頻度で開催されていますか。
たかせさん:「おむすび講座」は、企業や地方自治体などからのオファーに応じて、都度開催しています。今までの累計開催数は、およそ70回です。


「みんなの放課後食育教室」は、コロナ前までは東京都日野市にて毎週水曜日に小学生向けの料理教室を開催していました。また、コロナ禍では食材を家に配送し、作成した動画を見ながらご家庭で料理に取り組んでもらうスタイルで2年ほど実施していました。
――食育STEAM授業について、「Arts」の要素が加わることの影響を教えてください。
たかせさん:授業では、地域の郷土料理を調べ、調理実習で体験し、子供達が自ら100年後に残る郷土料理を考えるという内容です。料理はサイエンスの要素が大きいのですが、地域の食材を組み合わせて料理を考えたり、プレゼン資料を作ることはアートの要素が大きいと思います。

――事業を始めるきっかけとなった原体験があれば教えてください。
たかせさん:娘が小学生の頃に友達と遊ぶ際、何か食べるものを持たせようかと話していたところ、友達はコンビニで買うという話を聞きました。専業主婦の方でも添加物の多いコンビニ弁当を与えている現実を目の当たりにし、子どもたちを取り巻く食環境の不平等さについて考えるようになりました。コンビニ弁当を選んだ背景には何か事情があったかもしれませんが、コンビニ弁当が身体に与える影響を理解してその選択をしているのか疑問に思ったのです。日本は世界的にも添加物の規制が緩く、食の安全性について考えさせられます。きちんと知識があるのであれば良いですが、そうでない場合、その子どももそうした知識を得る機会が無いまま大人になる可能性が高く、こうした現状を変えたいと思いました。
また、私も母親になって実感しましたが、働きながら子どもの生活を守っているお母さんの負担が大きいなと感じます。お母さんたちがもっと余裕を持てるような環境になれば良いなと思ったことも、事業を始めるきっかけの一つです。子どもがお米を炊いて、おみそ汁を作れるだけでも、お母さんの負担は減ります。それは家族の平和に繋がるだけでなく、子どもにとっても料理をすることが成功体験となって自信になり、自己肯定感を育む機会になると考えました。そして、そこで育まれた力は、生き抜く力を養う一助にもなると思っています。
活動背景には、子どもの孤食や失われる日本食文化などの課題
――活動の背景には、どのような社会課題が挙げられますか。
たかせさん:子どもの孤食や、地域の食文化の継承問題があります。食文化については、活動する中でも「ご飯を炊いたり、おみそ汁を作ったりするのは面倒」という声をよく耳にしますし、米の文化が離れているのを実感します。
その他、食に対するリテラシーの低さも懸念しています。例えば、短気な子どもが増えている背景には小麦や白砂糖の影響があったり、添加物の多い食事が身体の負担になったりしていることを知らない親も多いように感じます。こうした状況は子どもたちを危険にさらしていると思います。また、食が欧米化したことによる生活習慣病の増加問題などもありますが、病気や妊娠など何かきっかけが無ければ食について学ぶ機会は無く、義務教育だけでは食に対するリテラシーの向上が望めないことも問題だと思います。加えて、学ぶ機会に恵まれても、多くの情報が溢れているので、それらを精査することが難しい社会だなと思っています。
――子どもの孤食について、その弊害をどのように感じますか。
たかせさん:一人で食べていると、おそらくテレビを見ながらの食事になるなど、食事をすることに集中できず味がどうかといったことを考えなくなるのではないかと思います。また、手作り料理が用意されていたとしても、その地域や家庭で受け継がれている料理や旬の食材についての知識を食事から得る機会が無くなる恐れもあると思います。人と食事を共にすることで、味や食感について共有し、きちんと食事と向き合える時間がつくられていくのではないかと考えています。
共働きが増える中で孤食問題は仕方がない状況になっていると思いますので、休日には共に食卓を囲んだり一緒に料理をしたりと、365日孤食にならないようにできたら良いですよね。
――食文化の継承について、活動をされている日野市内で失われようとしている食文化があれば教えてください。
たかせさん:日野市は都内の中では比較的農地が残っていると思いますが、相続問題などによる農地の減少や、都市農業の大変さによって農業をやめてしまう方も増えています。特に田んぼの減少を実感していて、一般の方が日野産のお米を入手するのは難しくなっていると思います。
――徳島県などの活動では、郷土料理が失われているのを感じますか。
たかせさん:郷土料理の一覧がありますが、同じ徳島の中でも海側や山側など地域によっても知識に差がありますし、子どもだけでなく大人が知らないことも珍しくありません。おそらく伝える術がなく、知る機会がなかったのかと思います。
――課題の解決にあたり、行政だけでなく社会的企業・NPOなど民間の力が必要になるのはなぜでしょうか。
たかせさん:行政が行っている活動では、食育が行き届かないと思います。例えば、貧困層であれば行政独自で子ども食堂やフードバンクなど支援していると思いますが、該当しない子どもたちが放置されてしまうことが気がかりです。一見して問題を抱えていない子たちは、自分で拾えるものしか学ばず、食についての知識を得る機会もないと感じます。
また、学校の授業に家庭科学習はありますが、食育に関する内容は薄く、カリキュラム自体も古くて現代とのギャップを感じますし、身につけてほしい食の学びからはかけ離れているなと思っています。コロナ禍では調理実習が無くなることもありましたが、本当に基本的な「ご飯を炊くこと」「おみそ汁を作ること」に立ち返り、これらは難しくないということをぜひ体験してほしいと考えています。そして、それが身につけば何とかなるということを義務教育の中で伝えられると理想的だと思っているのですが、職員次第で学校ごとに学びに差が生じているのが現状なので、そこに民間の力が必要だと考え、活動を行っています。
食を通じた自立、美味しい食事から得られる幸福感を伝えたい
――活動をする上で最も大切にしていることは何でしょうか。
たかせさん:「食を通して自立すること」「美味しい、温かい食事をする幸福感を伝えていくこと」を大切にしています。あたたかく美味しい食事には満足感を得る力があると思っていて、いじめや戦争ですら、食べ物の力をうまく利用すれば解決できると本気で考えています。きちんとした食事は健全な精神に繋がり、自分が満たされていれば他害行為をしようとは思わなくなるのではないでしょうか。食についての知識を当たり前に身につけていくことで、そうしたことに気がつけるようになっていけば良いなと思っています。
――今後の活動方針や新しく取り組みたいことなど、具体的な展望がありましたらお教えください。
たかせさん:全国の小学校に呼んでもらい、郷土料理などの伝承を手伝いたいと思っています。スケジュール次第では最短1週間程度あれば段取りは可能ですので、食育活動をお考えの際にはぜひご相談いただけると嬉しいです。
――最後に、今ニュースとして特に発信したいことはありますか。
たかせさん:図書館向けのシリーズ本なのですが、いま・生きる・ちからシリーズ『じぶんでできた! お弁当の本 (単行本)』を出版しています。小学生の男の子でも飽きずに読んでもらえるよう、マンガを入れたりストーリーを作ったりと工夫したので、読みやすいと思います。家庭で気軽に買える価格設定ではないかと思いますが、学校などに置いていただけたら嬉しく思います。
書籍情報: (著)杉崎 聡美 (監修)竹下 和男 (出版年月日) 2023/01/17 (定価)税込3,960円
「一般社団法人きほんの木」を支援する方法
たかせさん:ホームページより寄付を募っておりますので、ご支援いただけると助かります。また、「おむすび講座」などのご依頼も随時受け付けておりますので、食育活動をお考えの際にはぜひご相談ください。
【問合せ先】https://ecolle-ocatte.studio.site/kihonnoki