
社会課題解決の現場で働く方々からお話を伺い、その内容をインタビュー記事として発信するWebメディア「ソーシャルウォーカー(Social Walker)」。市⺠活動やソーシャルビジネスに焦点を当て、事業内容や背景にある社会課題、行政だけでは課題が解決されない理由などを独自インタビューを基に発信しています。
第13回目は、「株式会社遭遇設計」の代表取締役である広瀬 眞之介さんにお話を伺いました。
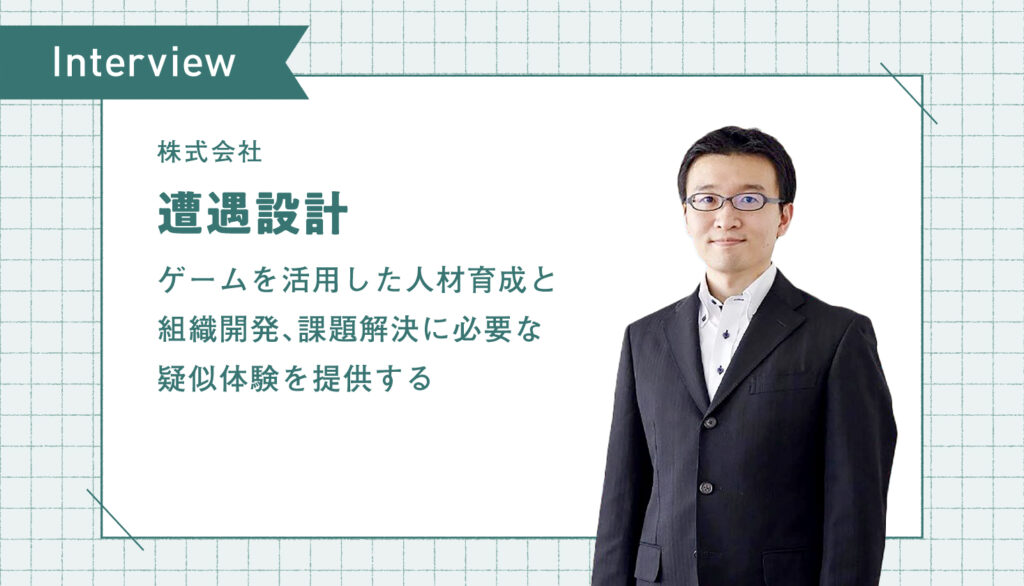
ゲームでありながら、娯楽ではなく、現実に存在する課題の解決を第一の目標とする”シリアスゲーム”。メンタル不調者との接し方、学校のいじめ対応、VIPへの営業など取り扱うテーマが重大な局面なものであっても、ゲームだからこそ失敗が許され、疑似体験を通じて学びを深めることができます。
株式会社遭遇設計では、そんなゲームの良さを活かして、通常は直接体験するのが難しい体験を、疑似体験できるゲームの開発を通して、人材育成・組織開発の課題解決に取り組んでいます。
団体紹介

| 名称 | 株式会社遭遇設計 |
| 公式HP | https://so-guu.com/ |
| 事務所所在地 | 東京都文京区小石川3丁目 26-2番 |
| 問合せ先 | https://so-guu.com/contact/ |
| 事業内容 | 人材育成及び組織開発のための、コンサルティング・研修・ツール開発・事業創出など |
今回お話を伺った人

広瀬 眞之介(ひろせ しんのすけ)さん
「株式会社遭遇設計」代表取締役
■プロフィール
ゲーム作家、産業カウンセラー、研修講師、コミュニティマネージャー、事業創造コンサルタント
イノベーティブなコンセプト/サービスづくり多数。その経験を元に体験型学習を通じた人材育成を行う。実務・実生活で使える学びが得意。
ゲーム研修『ウツ会議』は、参加者の約70%がうつ病に対処可能に。専門学校のゼミでは約90%が夏休み前に正社員内定。
代表作は、ネコワーキング(掲載:産経新聞)/『ウツ会議』(掲載:NHKおはよう日本・日経ムック)/『カウンセリングの極意』『ジョブクラフティング』(東京大学と共同研究)など。
――広瀬さん、本日はどうぞよろしくお願いします。
広瀬さん:よろしくお願いします。
ゲームだからこそ可能な、疑似体験を通した実践的な学び
――はじめに、「株式会社 遭遇設計」の事業内容を教えてください。
広瀬さん:主な事業は、人材育成やチームビルディングに活用できるカードゲーム・ボードゲームの開発と、それらを用いた研修・ワークショップの提供です。一例として、メンタルヘルス研修の『ウツ会議』や、カウンセリングを心理職以外の方にも知ってもらうことを目的に東京大学と共同開発した『カウンセリングの極意』、地域にもっと愛着を持ってもらいたいと開発した地域活性ゲーム『地方想生』といったラインナップがあります。
このような研修用ゲームを扱う企業は他にもありますが、自社製品のみを提供するか、提携企業の製品のみを提供している場合がほとんどです。しかし我々の場合は、自社開発のゲームに加え他社製品も取り扱っており、現在32種類のゲームを提供しています。その内訳は、自社開発製品が約半分の16種類、残りが他社製品です。幅広く商品を取り扱っているため、ゲーム型の研修・ワークショップの中でも、ニーズに合わせて最適なものを提供できることが我々の特徴でもあります。
また、一気通貫で、企画・開発・営業・提供までする、という点も特徴の一つです。これらを一気通貫で行っている企業はあまりありません。そのため、我々には様々な立場の知識や経験が溜まりやすく、それが質の良いサービスに繋がることで、その目利き力を喜んでいただけることが多いです。
――活動の対象は全国でしょうか。
広瀬さん:はい、お声がかかれば全国どこへでも。北海道へ行くこともありますし、よく広島の教頭会に呼んでいただいて、メンタルヘルス研修を行っています。ご要望に応じ、オンラインでの研修開催も可能です。
――広島での実績以外に、導入実績を伺えますか。
広瀬さん:海上自衛隊やポルシェジャパンなどでの導入実績があります。研修内容としては、管理職向けの研修が多いです。
――代表作の一つである『ウツ会議』について、メンタルヘルス研修をゲーム化しようと思いつかれた理由を教えてください。
広瀬さん:現在の事業を行う前に、メンタルヘルス研修にゲストとして呼ばれる機会があったのですが、行ってみるとメンタルヘルス研修は不人気で、参加者の心理的ハードルが高いということに気がついたのです。こうした状況をどうにかできないかと考えた時に、メンタル不調の体験がないのに、医者やカウンセラーの話を聞いても響かないなと思いまして。そこで、うつ病の疑似体験ができないか、と思い至ったのです。
疑似体験をするには3つの方法があり、1つ目は映画や漫画・小説などの「ストーリー」、2つ目は枠がない画像を体験できる「VR」、3つ目が「ゲーム」です。この3つの中から、自分ができそうだと思ったものがアナログゲームだったため、ゲーム開発に挑戦することに決めました。そして完成したのが、“うつ病の人をどのように助けるか”を疑似体験できる『ウツ会議』です。うつ病の人を助ける経験は滅多にできませんし、実際に行うとなると大変な上、失敗するわけにもいきません。しかしゲームであれば現実世界の責任が連動しないので、何度でも失敗することができます。取り組みにくい体験や希少な体験を疑似体験できることは、救われる人の増加に繋がっていくと考えています。

――『ウツ会議』開発時の苦労話などあれば教えてください。
広瀬さん:いろいろありますが、現実をどの程度再現するか、という点が難しかったです。例えば、ゲームでは症状カードでタワーを作っていくのですが、そのカードの中に“ホームで電車に吸い込まれそうになっている”カードがあります。健康な人でも人によってはショックを受ける内容ですが、実際にそのようなことがあるという事実を知ってもらう必要もあります。どこまでを学びとして入れて良いのか、また、絵柄一つとってもどの程度デフォルメするか、とても難しかったです。
――『ウツ会議』の反響はいかがですか。
広瀬さん:『ウツ会議』は、うつ病患者の周りの人たちが、患者をサポートできるようになることを目的としたゲームで、うつ病を患っている当事者やストレスチェックシートの数値が高い人にはご遠慮いただいているゲームです。しかし、今でも稀にではありますが、「メンタルヘルスをそんな気軽なものにして良いのか」「うつ病で遊ばないで欲しい」というようなお声をいただきます。その度に、まずは学ぶハードルを下げ、簡単で取り組みやすいところからメンタルヘルスについて知る機会があっても良いと考えていること、患者を揶揄したり、苦しめたりといったこととは真逆の想いで作っていることを伝え続けているのですが、“ゲーム=エンタメのみ”と誤解される方はいらっしゃいます。
一方で、ゲームに参加した6〜7割の方からは「うつの対応ができるようになった」とのお声をいただきます。3時間ほどのゲーム研修で、メンタル不調者の基礎的な対応の仕方が“分かるようになった”ではなく“できるようになった”と言っていただくことができ、これはゲームを通した疑似体験だからこその学びだと思うし、そのようなものを作れて良かったと思っています。
ゲームにすることで、専門的な学びでも誰もが気軽に受けられる
――活動の背景には、どのような社会課題が挙げられますか。
広瀬さん:仕事に関する悩みを抱えている人が多いことや、専門的な研修の機会が普及していない現状があると思います。
仕事に関する悩みについては、産業カウンセラーとしてカウンセリングを行う中でさまざまな立場の人の話を聞き、働くことに対する悩みの多さにも気づきましたし、私自身がうつ病を発症してドロップアウトした経験もあります。企業が抱える問題として、人材育成にかかる全体的なコストの高さや、人が辞めていくことを前提とした労働環境になっているなと思い、それは勿体ないなと思いました。
また、私が働けない頃に、社内研修の機会に対して不満を漏らす会社員に出合い、自分は喉から手が出るほど欲しいと思っている社会人としての学びの機会に対して不満を抱く姿に、ミスマッチが起こっているなという問題意識が芽生えました。加えて、仕事と同じ状況を再現できるようなことが手軽に行えたら、働くことにまつわる様々な問題が変わっていくのではないか、と考えるようになりました。そして、どこかの正社員にならないと得られないような研修をできるだけ流通可能にしたいと思った時、その手段としてボードゲームという発想に至りました。
――課題の解決にあたり、行政だけでなく社会的企業・NPOなど民間の力が必要になるのはなぜでしょうか。
広瀬さん:私たちの考え方としては単純に、税金を使う方が良いのか、民間のお金を使う方が良いのかを分けて考えています。民間の中に存在する「メンタルヘルス研修をしたい」というようなニーズは、そのまま取りに行った方が良いと思っていますが、逆に活動の中には行政のお墨付きやお金を使った方が良いだろうという活動もあります。
一例として、文京区さん・三井不動産さんと共に実施した「多世代ボードゲーム会」を紹介します。こちらのイベントは、ボードゲームを通じて地域の人々と交流し、親睦を深めようという多世代交流が目的のイベントです。市区町村の行政には地域の担い手が古い人や決まった顔ぶれになってしまうので、若い人や新しい人を入れていきたい、といったニーズがあります。しかし、多世代交流を謳って集客を行うとなかなかターゲットの人が集まらない。そのため、6つのターゲット向けにイベントの見せ方を変えて集客を行い、全員を混ぜてイベントを開催します。これは現代アートの手法を真似していて、それぞれに異なる興味関心を持った幅広い世代の人々が交流できる仕掛けになっています。来場した方々は最初面食らっていますが、ゲームが始めればその相手は誰でも良いことに気づき、勝手に仲良くなっていただけます。

このようなイベントでは、集客時にやや騙している形になりますが、安全なイベントであるという担保として行政などの後援に求めています。これがあることで怪しい団体などと差別化することもでき、参加者の安心感にも繋がります。私たち零細企業には出しにくい信頼性を行政が後援することで作ってもらい、その逆に、行政が難しい部分は私たちが引き受ける。このように、行政と民間それぞれが互いの得意・不得意を補い合い、協働していけることが望ましいと考えています。
数多くある研修系ゲームが失われないためのミュージアムを
――今後の活動方針や新しく取り組みたいことなど、具体的な展望がありましたらお教えください。
広瀬さん:現在、社内で世の中にある研修系ゲームを500種類ほどリストアップしているのですが、売れ行きが伸びないことや権利関係の不明確さなどの理由から、失われていってしまうゲームも存在します。そこで、研修系ゲームのミュージアムをアカデミックな拠点として設立し、数多くあるゲームが失われないようにしていきたいと考えています。
――最後に、今ニュースとして特に発信したいことはありますか。
広瀬さん:今までは、取り扱っているゲームを単体で研修やワークショップにて提供することが多かったのですが、今後は複数のゲームを目的に合わせて組み合わせ、提供していく予定です。例えば、DIY「組織開発キット」「人材育成キット」「社内コミュニケーションキット」といったパッケージを作り始めています。
「株式会社 遭遇設計」を支援する方法
広瀬さん:多くの人に、ゲームを通した実践的な学びを体感していただけたら嬉しく思います。研修のご希望など、お気軽にお問い合わせください。
【問合せ先】https://so-guu.com/contact/